夏休みの宿題で、毎年親子ともに頭を悩ませるものといえば「読書感想文」ですよね。特に、学校から指定された課題図書にお子さんが全く興味を示さず、「こんなの、読みたくない!」と宣言されてしまうと、親としては本当に途方に暮れてしまいます…。
「無理やり読ませたところで、きっと良い感想文なんて書けないだろうし…」 「かといって、やらないわけにもいかないし、一体どうすれば…」
わかります!その気持ち、痛いほどよくわかります。私自身も以前、子供が課題図書の分厚さを見ただけで「絶対無理!」と泣きそうになっていたのを見て、親子で途方に暮れた経験があるんです。
この記事では、そんな**読書感想文の課題図書を「読みたくない」**という切実な問題に直面している親御さんに向けて、お子さんの気持ちに寄り添いながら、親子でストレスなくこの大きなミッションを乗り切るための「タイパ(タイムパフォーマンス)重視の裏ワザ」を、私の体験談も交えながら具体的にご紹介します。
この記事のポイント ・ 無理に「全部読め」と言わない ・ 読書への心理的ハードルを下げる裏ワザを活用 ・ 「感想」ではなく「連想ゲーム」で書くネタを探す ・ 親子で協力して「作業」として効率的に終わらせる ・ 最終手段は「ほとんど読まなくても書ける」方法に頼る
なぜ子供は課題図書を「読みたくない」のか?まずは気持ちに共感しよう
いざ解決策!と行きたいところですが、少しだけ立ち止まって考えてみてください。なぜ、お子さんは課題図書を「読みたくない」と感じるのでしょうか。その気持ちを頭ごなしに否定せず、「そっか、読みたくないんだね」と一度受け止めてあげることが、実は解決への一番の近道だったりします。
「面白そうじゃない」という正直な気持ち
子供にとって、本は「面白いから読む」ものです。普段読んでいるマンガや、ワクワクする冒険小説と比べて、課題図書はなんだか表紙も地味だし、タイトルも難しそう…。大人にとっては素晴らしい名作でも、子供の目には「面白くなさそうなお勉強」と映ってしまうのは、ある意味当然のことかもしれません。
これは、大人が「体にいいから」と勧められても、苦手な野菜をなかなか食べられないのと同じ心理ですよね。頭では「やった方がいい」と分かっていても、心が動かなければ、なかなか手は伸びないものです。
他の遊びや習い事で忙しくて時間がない
今の子供たちは、私たちが子供だった頃よりもずっと忙しい毎日を送っています。学校の宿題はもちろん、習い事、友達との遊び、YouTubeやゲーム…。限られた夏休み時間の中で、やりたいことは山ほどあります。
そんな中、興味の持てない本に何時間も費やすのは、子供にしてみれば「もったいない!」と感じるのかもしれません。この「タイパ」を重視する感覚は、実は大人だけでなく子供も持っているんですよね。
そもそも本を読むのが苦手、活字が嫌い
そして、一番シンプルかつ根深い理由がこれです。活字を追うこと自体が苦手だったり、本を読む集中力が続かなかったりするお子さんにとって、読書は楽しい娯楽ではなく、骨の折れる「作業」です。
私自身も、子供の頃は読書がそれほど好きではなく、本を1冊読み終えるのにものすごくエネルギーが必要でした。そんな子にとって、「分厚い本を読んで、さらに感想まで書きなさい」という課題は、まるで目の前にとてつもなく高い壁がそびえ立っているように感じられるのです。
まずはこれらの気持ちに「そうだよね、面白そうに見えないもんね」「ゲームする時間、なくなっちゃうもんね」と寄り添ってあげるだけで、お子さんの頑なな気持ちが少しだけ和らぐはずです。
【タイパ重視】課題図書を少しだけ読んで感想文を仕上げる裏ワザ5ステップ
お子さんの気持ちに寄り添えたら、いよいよ実践編です。ここでは、読書感想文の課題図書を読みたくないお子さんでも、最低限の労力で感想文を形にするための、タイパ抜群の裏ワザを5つのステップでご紹介します。
これは「ズル」ではありません。興味を持つための「きっかけ作り」であり、ゴールにたどり着くための「作戦」です。親子で一緒に、ゲーム感覚で取り組んでみてください。
ステップ1:「表紙・帯・目次・あとがき」だけ親子で一緒に読む
いきなり本文から読み始めるのは、ハードルが高すぎます。まずは、本全体を「知る」ことから始めましょう。
- 表紙と帯を見る: どんな絵が描かれている?どんなキャッチコピーが書かれている?「面白そうだね」「この子、悲しそうな顔してるね」など、見たままの感想を口に出してみます。
- 目次を読む: 章のタイトルを眺めるだけで、物語がどんな風に進んでいくのか、大まかな流れが見えてきます。推理小説の目次を見るような感覚で、「この章がクライマックスかな?」なんて予想するのも楽しいです。
- あとがき・解説を読む: ここには、作者の想いや、物語の背景、伝えたいメッセージなどが凝縮されています。いわば、映画のパンフレットのようなもの。ここを読むだけで、作品の「一番おいしいところ」をカンニングできちゃいます。
全部合わせても15分もかかりません。これだけでも、「なんとなく、こういう話なのかな?」という地図が頭の中にできあがり、この後のステップがぐっと楽になります。
ステップ2:ネットの「あらすじ」や「書評サイト」で全体像をざっくり掴む
次に、文明の利器を最大限に活用します。インターネットでその本の「あらすじ」や「書評」「ネタバレ」を検索してみましょう。
ここで大切なのは、**「丸写しするため」ではなく、「物語の要点を理解するため」**に使うことです。私自身も、忙しくて本を読む時間がない時は、映画のレビューサイトを見て「今度これ観ようかな」と当たりをつけたりしますよね。あの感覚です。
「〇〇(本のタイトル) あらすじ」で検索すれば、たくさんのサイトが出てきます。親子で一緒にいくつかのサイトを眺めながら、「へぇ、主人公はこんな大変な目に遭うんだ」「最後はこうなるんだね」と、答え合わせをするように物語の全体像を掴んでしまいましょう。
ステップ3:印象に残りそうな登場人物を一人だけ決める
物語全体をぼんやりと把握したら、次は焦点をぐっと絞ります。感想文を書く上で、一番簡単なのは「登場人物」にフォーカスすることです。
あらすじや書評を読んでみて、「この主人公、自分と似てるかも」「この意地悪なキャラクター、気になるな」「この脇役、いいこと言うな」など、お子さんが少しでも心に引っかかった登場人物を一人だけ選びます。
物語全体について書こうとすると、話が散らかってしまいますが、「〇〇くんという登場人物について」というテーマを最初に決めてしまえば、書くべきことが明確になり、感想文の骨組みが作りやすくなります。
ステップ4:「もし自分だったらどうする?」で感想のタネを無理やりひねり出す
ここが、感想文の「感想」を生み出すための最重要ステップです。ステップ3で決めた登場人物になりきって、「もし自分だったら?」という視点で物語を捉え直してみましょう。
- 「〇〇くんが、友達にあんなひどい事を言われた場面、もし自分だったら、言い返すかな?それとも黙っちゃうかな?」
- 「主人公が、たった一人で冒険に出る決心をしたけど、自分だったら怖くてできないかも。すごい勇気だな」
- 「この登場人物の行動、全然理解できない!自分だったら絶対こうするのに!」
ポイントは、「立派な感想」を言わせようとしないことです。「ムカつく」「すごい」「ありえない」といった、子供の素直な感情を引き出すだけで十分。それが、オリジナルの感想の貴重なタネになります。
ステップ5:親子で会話しながら構成メモを作る(箇条書きでOK!)
さあ、最後の仕上げです。ステップ1から4で集めた材料を元に、感想文の設計図となる「構成メモ」を作りましょう。ここでも、お子さんに一人でやらせる必要はありません。親がインタビュアーになって、会話形式で進めるのがおすすめです。
<構成メモの例>
- はじめ(きっかけ): この本を読もうと思った理由(課題図書だから)、表紙を見て思ったこと
- なか(あらすじと感想):
- この本は、〇〇という主人公が△△するお話です。(ネットで調べたあらすじ)
- 僕が一番心に残ったのは、〇〇という登場人物です。
- なぜなら、□□という場面で、すごいと思ったからです。(ステップ4で出た感想)
- もし自分だったら、〇〇くんみたいにできずに、たぶん泣いてしまったと思います。(ステップ4で出た感想)
- おわり(まとめ・学び): この本を読んで、〇〇ということを考えました。これから自分も、□□なことを大切にしたいです。
このように、親が質問しながら子供の言葉をメモに書き出していくだけで、あっという間に感想文の土台が完成します。あとは、このメモを見ながら原稿用紙に清書するだけ。ここまでくれば、ゴールはもう目の前です。
これで文字数も怖くない!感想文のネタを広げる魔法の質問集
上記のステップで骨組みはできても、「原稿用紙が全然埋まらない…」という問題に直面することもよくありますよね。そんな時は、親が「魔法の質問」を投げかけて、お子さんの言葉をさらに引き出してあげましょう。
「この中で一番好きな(嫌いな)登場人物は誰?それはどうして?」
「好き・嫌い」という感情は、感想文の強力なエンジンになります。「なぜ好きなのか」「どこが嫌いなのか」を深掘りするだけで、自然と文字数は増えていきます。「優しいから」という答えが返ってきたら、「どんなところが優しいと思った?」とさらに質問を重ねるのがコツです。
「この本の結末、変えてもいいならどんなお話にする?」
この質問は、お子さんの創造力を刺激します。「本当はハッピーエンドが良かった」「もっと悪いやつは懲らしめられてほしかった」など、自由な発想で「IFの物語」を考えさせてみましょう。元の物語と比較することで、「作者はなぜこの結末にしたのか」という、一歩進んだ考察に繋がるからです。お子さん自身の「こうだったら良かったのに」という願望こそが、他の誰にも書けない、あなただけの感想文の源泉になります。
「もし主人公が、うちのクラスに転校してきたら人気者になると思う?」
この質問は、物語の世界と、お子さんの現実の世界を繋げるための魔法の架け橋です。架空の登場人物を、自分の日常に引き寄せて考えてみることで、キャラクターへの親近感が一気に増します。
「〇〇くんは、運動神経が良さそうだから、すぐ人気者になりそう」「△△さんは、ちょっと静かだから、最初は友達ができないかも。でも、私が話しかけてあげる」など、具体的な想像が膨らめば、その人物像についてより深く、生き生きと書き表すことができるようになります。
「この本で一番『そりゃないよ!』って思った場面はどこ?」
感想文は、必ずしも共感や感動ばかりを書く必要はありません。むしろ、「納得できない」「それはおかしい」と感じた部分こそ、強いオリジナルの意見になります。
お子さんが物語に対して抱いた違和感や反発は、物事を批判的に見る力(クリティカルシンキング)が育っている証拠です。その「モヤモヤ」を大切にしてあげてください。「主人公の行動は、自分には理解できなかった。なぜなら…」と書けば、それはもう立派な批評であり、深みのある感想文になります。
親はどこまで手伝う?頑張りすぎないための心の持ち方
ここまで様々な裏ワザをご紹介してきましたが、多くの親御さんが最後に悩むのが「どこまで手伝っていいの?」という線引きだと思います。手伝いすぎると子供のためにならない気がするし、かといって突き放すわけにもいかない…。この問題、本当に悩ましいですよね。
感想文の主役は子供!親はあくまで黒子に徹する
大前提として、感想文を書く主役は、あくまでお子さん本人です。親の役割は、選手としてグラウンドに立つことではなく、選手の能力を最大限に引き出す「コーチ」や「マネージャー」です。
具体的には、
- 良い質問を投げかけて、考えを深める手伝いをする
- 子供が話した言葉を、メモに書き起こして整理してあげる
- 「てにをは」がおかしい部分を、一緒に見直してあげる
といったサポートに徹しましょう。親が「こう書くべきだ」と答えを与えてしまうと、お子さんは自分で考えることをやめてしまいます。私たちは、あくまでお子さんの頭の中にある宝物を、外に出すお手伝いをするだけ、というスタンスが大切です。
完璧を目指さない!「正しさ」よりも「終わらせること」を優先しよう
これは、私自身が過去の失敗から学んだ、一番お伝えしたいことです。以前の私は、子供の感想文の文章が少しでもおかしいと、「その表現は正しくない」「もっと良い言葉があるはず」と、つい口を出してしまっていました。その結果、子供はすっかり書くのが嫌になり、親子関係までギスギスしてしまったのです。
その反省から、「100点の感想文」を目指すのをやめました。多少つたなくても、誤字があってもいい。まずは、「最後までやり遂げた!」という達成感を親子で味わうことの方が、子供の自己肯定感を育む上ではるかに重要だと気づいたのです。特に共働きで時間がない中、完璧を目指すと親子で疲弊してしまいます。まずは「終わらせる」ことを目標にしてみませんか。
「すごいね!」「面白い考えだね!」褒め言葉のシャワーでやる気にさせる
どんな些細なことでも、お子さんが自分の意見を口にしたら、「すごいね!」「面白い考え方だね!」「そんなこと、お母さん全然気づかなかったよ!」と、全力で褒めてあげてください。
大人から見れば稚拙な意見かもしれません。でも、お子さんにとっては、一生懸命考えた言葉です。そのプロセスを認めて褒めてあげることで、「自分の考えを言ってもいいんだ」「書くのって、意外と楽しいかも」という前向きな気持ちが芽生えてきます。褒め言葉のシャワーこそが、お子さんの「やる気スイッチ」を押す最強のツールなのです。
### まとめ
・ まず子供の「読みたくない」という正直な気持ちに共感する ・ タイパ重視の裏ワザを使い、読書への心理的ハードルを下げる ・ 親はあくまでサポーターに徹し、決して完璧を目指さない ・ 魔法の質問を通じて、子供自身のユニークな言葉を引き出す ・ 親子で協力し、大変な宿題を「楽しい共同作業」に変える
「読書感想文の課題図書を読みたくない」という問題は、多くのご家庭が通る道です。お子さんの気持ちを頭ごなしに否定せず、「そっか、読みたくないんだね」と受け止めてあげることが、このミッションを乗り切るための何より大切な第一歩です。
全部を完璧にこなそうと頑張りすぎず、今回ご紹介したような裏ワザも上手に活用しながら、大変な宿題を親子の絆を深めるイベントに変えていきましょう。この記事が、少しでも皆さんの夏休みの負担を軽くするお手伝いができれば、心から嬉しく思います。
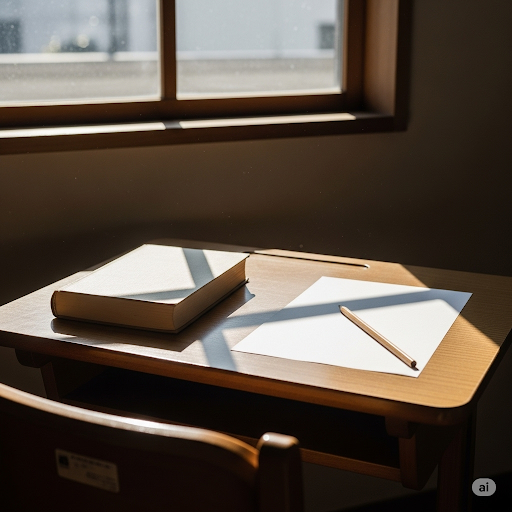
コメントを残す